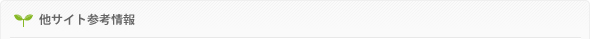仁和寺庭園 にんなじ
庭の概要
| 所在地 | 京都市右京区御室大内 |
|---|---|
| 電話 | 075-461-1155 |
| 作庭年代 | 江戸時代中期~後期 |
| 作庭者 | |
| 様式 | 池泉式、露地 |
| 寺社の創建年代 | |
| 文化財指定・登録状況 | 京都市の名勝 |
| 敷地面積 | 4,106.5㎡(文化財指定部分) |
| 公開状況 | 公開(有料)(宸殿の庭のみ。飛濤亭・遼廓亭は通常非公開。) |
歴史・いわれ
 宸殿から北東方向をみる。飛濤亭(中央手前)と遠方の五重塔が奥行きを感じさせる。
宸殿から北東方向をみる。飛濤亭(中央手前)と遠方の五重塔が奥行きを感じさせる。
仁和寺は、双ケ丘の北に位置する寺院で、その起源は平安時代の仁和2年(886年)に光孝天皇の勅願寺として起工されたことに始まります。光孝天皇は起工の翌年に亡くなりますが、次代の宇多天皇によって工事は進められ、仁和4年(888年)に落成の供養が催され、年号をとって仁和寺と名付けられました。その後、退位した宇多上皇が出家、仁和寺第1世となって以後、代々皇族が門跡となった門跡寺院としても著名です。
平安時代から鎌倉時代にかけて、多くの子院を抱え、隆盛を誇った仁和寺には、法金剛院の庭にある「青女の滝」の滝石組を組み直した徳大寺静意などの石立僧がいたことから、庭園も作られていたものと思われますが、応仁・文明の乱により全山が灰燼と帰し、種々の史料も失われてしまったため、往時の状況ははっきりとわかっていません。
その後、16世紀に入ると徐々に復興が進められ、江戸時代の寛永年間(1624~1644年)に大々的な復興が行われます。金堂や御影堂などの建物が京都御所から移築され、ほぼ現在に見る寺観が整いました。
この寛永年間の復興の際に宸殿の庭園も営まれたと思われますが、今に見るような姿の庭園になったのは元禄年間(1688~1704年)のことと思われます。仁和寺に残る史料には白井童松という人物が作庭を行ったと記録されています。
さらに、江戸時代中期には茶室「遼廓亭」が、また江戸時代後期には茶室「飛濤亭」が建てられ、それぞれの茶室の周囲には露地庭が作られます。
近代に入ると、明治20年(1887年)に宸殿などを焼失してしまいますが、大正3年(1914)に宸殿が新たに建てられ、近代に京都を中心に活躍した造園家7代目小川治兵衛(植治)により庭園が改修されました。
宸殿の庭園は、宸殿に面して中央付近で大きくくびれ、石橋が架けられた池を前面に、背後の段上に設けられた茶室「飛濤亭」、さらに庭園の外に位置する中門や五重塔を望むことのできる構成で、池には滝石組が設けられ、涼やかな水音を立てて水が流れ落ちています。
特に大石を用いた滝石組は、法金剛院などの平安時代の庭園にしばしば見られることから、この滝石組も平安時代に遡るのではないかともいわれますが、はっきりしたことは解っていません。池の護岸石組は、立石の少ない穏やかな構成をしており、江戸時代前期に作られた、二条城二之丸庭園などの武家の庭園とは違う味わいの庭となっています。また、池から流れ出る遣水の軽快な意匠は、植治の手であることをうかがわせます。
見所・みどりの情報
庭園の景として、背後の建物を利用した構成は比較的珍しく、秋になると、池の手前の白砂敷に紅葉が映え、格別の美しさとなります。
宸殿の北西側にある「遼廓亭」は、江戸時代に活躍した画家の尾形光琳の遺愛の席を移したとも伝えられる建物です。そこに作られている露地庭は、北側に滝石組を備えた池と流れのある珍しい形式のもので、広々とした明るい感じに作られていますが、一方で、周囲の竹や高木が日差しを遮るため、落着いた雰囲気もかもし出すなど、千家の露地などとはまた趣の違う庭となっています。
宸殿の庭の池の北側の「飛濤亭」は、宸殿の庭より一段高くなった丘の上、宸殿の庭の池への深い流れを渡って辿り着くように作られており、深山幽谷の雰囲気を演出しています。また一方で、亭の前からは、宸殿とその庭が一望できるため、開放感もあわせもつなど、「遼廓亭」の露地庭と同じく、独特の趣をもった露地庭となっています。
このように、古い歴史と格式を誇る仁和寺の庭は、長い年月をかけて営々と作られてきた、それぞれに趣の異なった池庭と2つの露地庭が、違和感なく一体化して今に残されている点で貴重なものとなっています。
文化財の指定/関連の文化財
宸殿の庭と、「飛濤亭」「遼廓亭」の露地が一体として、平成8年(1996)に京都市の名勝に指定されています。
境内全体は昭和13年(1938年)に国の史跡に指定されており、さらに平成6年(1994年)12月、世界文化遺産に登録されました。
仁和寺には有名な御室のサクラがあります。普通のサクラよりも背丈が低く、幹が何本にも分かれているのが特徴で、大正13年(1924年)に国の名勝に指定されています。
ご注意
霊宝館では、仁和寺に伝わる様々な寺宝が公開されています(4月1日~5月第4日曜日、10月1日~11月23日)。詳しくは仁和寺のホームページをご覧ください。
飛濤亭・遼廓亭は事前に申し込んで拝観することができます。日程や人数に制限がありますので、詳しくは仁和寺のホームページをご覧ください。
引用・参考文献・資料提供
【引用・参考文献】・御室御所之全図、江戸時代末期
・京都御室大内山仁和寺眞景、明治30年代
・仁和寺殿舎再建記坤、大本山仁和寺、1915
・保勝会一覽昭和四年十月現在、保勝会
・御室餘光、仁和寺、1930
・宇多天皇一千年弘法大師一千百年御忌紀要、眞井覺深、1932
・日本庭園史圖鑑第八卷、重森三玲、1936、有光社
・日本庭園史圖鑑第十七卷、重森三玲、1937、有光社
・京都名園記中、久恒秀治、1968、誠文堂新光社
・日本庭園史大系第15巻江戸初期の庭(2)、重森三玲・重森完途、1972、社会思想社
・日本庭園歴覧辞典、重森三玲、1974、東京堂出版
・日本史小百科19庭園、森蘊、1984、近藤出版社
・京の茶室西山・北山編、岡田孝男、1989、学芸出版社
・京都市の文化財第14集、京都市文化財保護課、1997
・京都・山城寺院神社大辞典、1997、平凡社
・中根金作京都名庭百選、1999、淡交社
【取材協力および資料提供】
仁和寺