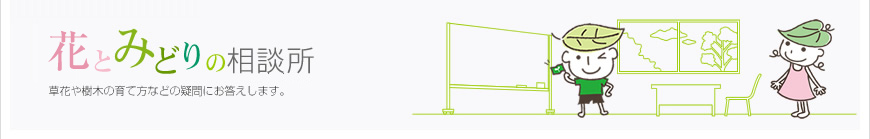花とみどりの相談所だよりQ&A
- Q. <トゲチシャ> 数年前から、道路の側や空き地に生えている雑草ですが、今年は特に沢山目立ちます。見ようによっては面白い植物なので、名前と、どこから来たのかを教えてください。
- この植物はキク科の1〜2年草で、ヨーロッパの原産ですが、今ではほぼ全世界で見られるようです。学名を「ラクツカ・スカリオラ」といい、和名は「トゲチシャ」又は「アレチヂシャ」とつけられています。日本では1949年に初めて北海道で採集されましたが、現在は日本全域に広がっています。市街地や草地に多く、農耕地にはあまり侵入しないようですが、ご質問にあるように、関西地方では道路の緑地帯や街路樹の植樹帯などに群生しています。茎は直立し、葉は無柄で基部は耳状に茎を抱いて、ねじれて垂直につき、葉身は羽状に深く切れ込むため、確かに形は面白いかもしれませんが、茎や葉に固い刺(とげ)があるので取扱いはやっかいです。なお、葉に切れ込みのない変種も帰化していて、「マルバトゲチシャ」という和名がつけられています。
「1〜2年草」という語彙の説明をしますと、個体により、1年草になったり、2年草になったりする、という意味です。まず1年草とは、1年(365日)以内に「発芽・生長・開花・結実・枯死」するものをいいますが、2年草とは、以上の過程を1年以上2年以内に行うものを指します。トゲチシャの場合、早く発芽したり、生長が速いものは1年草となり、遅く発芽したり生長の遅れたものは2年草になります。園芸書などで「1・2年草」という記述がよく使われますが、これは1年草と2年草を合わせてまとめたもので、意味はまったく異なります。
- <写真>

トゲチシャの開花株
トゲチシャの未開花株
トゲチシャの開花状態