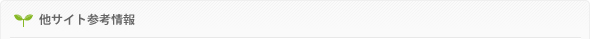ウェスティン都ホテル京都 葵殿庭園・佳水園庭園 あおいでん/かすいえん
庭の概要
| 所在地 | 京都市東山区三条けあげ(東山区粟田口華頂町) |
|---|---|
| 電話 | 075-771-7111 |
| 作庭年代 | 葵殿庭園:昭和8~9年(1933~1934年) 佳水園庭園:大正14~15年(1925~1926年) |
| 作庭者 | 葵殿庭園:小川治兵衛(植治) 佳水園庭園:小川保太郎(白楊) |
| 様式 | 葵殿庭園:池泉式 佳水園庭園:(流れの庭) |
| 寺社の創建年代 | |
| 文化財指定・登録状況 | 京都市の名勝 |
| 敷地面積 | 葵殿庭園1,225㎡、佳水園庭園335㎡(ともに文化財指定部分) |
| 公開状況 | 公開 |
歴史・いわれ
南禅寺や岡崎にほど近い華頂山のふもと、蹴上(けあげ)にあるウェスティン都ホテル京都は、1世紀以上の歴史がある京都の代表的なホテルです。明治23年(1890年)に開設された保養所・吉水園(よしみずえん)に始まり、明治33年(1900年)、洋式の宿泊施設「都ホテル」となりました。近代から現在に至るまで、徐々に建物の拡充が図られ、合わせて植栽や作庭が行われてきました。葵殿庭園と佳水園庭園は、そのホテルの歴史を反映しています。
 葵殿庭園。深山幽谷のような眺め
葵殿庭園。深山幽谷のような眺め(ウェスティン都ホテル京都提供)
 葵殿庭園の石組
葵殿庭園の石組(ウェスティン都ホテル京都提供)
 佳水園庭園。岩盤と流れによる独特の景観
佳水園庭園。岩盤と流れによる独特の景観(ウェスティン都ホテル京都提供)
葵殿庭園
葵殿の庭は、いくつかの段階を経て現在の姿になりました。もともと、京都を中心に活躍した造園家・7代目小川治兵衛(植治)が葵殿(主食堂)が建てられる以前の明治37年(1904年)に最初の作庭を行いました。この時には、華頂山の斜面を植栽し、建物からの眺めを整える程度の簡素なものだったようです。その後、この建物が葵殿として建て直された大正4年(1915年)にも造作が行われました。
今見るような姿にほぼ整えられたのは、昭和8年(1933年)に茶室(旧)「可楽庵」(からくあん)(後に場所を移して新たに設置)が造営された時です。再び植治が作庭に当たり、翌年にかけて工事が行われますが、植治は昭和8年の末に亡くなったため、後継の植木職人たちによって仕上げられました。
この作庭によって、簡素な庭が大きく変貌することになりました。一番の大きな変化は、琵琶湖疏水の水を使い、華頂山の斜面を大きく使って流れる2筋の滝流れと、流れを受ける池を造ったことです。滝流れはおそらく、葵殿(当時の主食堂)と(旧)可楽庵のために2筋にしたと考えられます。この雄大な滝流れと池によって、水量豊かなダイナミックな造りの庭園が完成しました。
滝石組などには、琵琶湖西岸に産する褶曲の目立つ独特の模様の石が多く使われていますが、植治はこの石を他の京都の庭園でもよく用いました。また、高木ではモミジが、低木ではサツキツツジの刈り込みが多く植えられ、植治様式ともいえる、近代に特徴的な軽快な雰囲気の庭園が完成します。
なお、平成4~5年(1992~1993年)に葵殿を含む旧本館の建て替え工事の際、池の護岸に手が加えられましたが、護岸石組の修繕や植栽の整備が行われ、植治の作庭当時の姿が取り戻されました。
佳水園庭園
一方、佳水園の庭は、葵殿の庭園から斜面を南に上がった場所にあります。庭はもともと「喜寿庵」(きじゅあん)と呼ばれ、大正期に総理大臣を務めた清浦奎吾(きようらけいご)の京都での別荘として、大正14~15年(1925~1926年)に造られたものです。この地に別荘の造営を勧めたのは、清浦内閣で逓信大臣を務め、後に都ホテルの社長に就任した藤村義朗らであったと、清浦は後に述懐しています。
作庭は植治の息子の小川保太郎(白楊)によって行われましたが、清浦の意向は、あまり大規模な工事にしないというものでした。現地は天然のチャートの岩盤が斜面に露出した岩山であり、白楊は大胆に岩盤をそのまま利用しました。白楊は、石造品や石の扱いについては、父の植治を凌ぐほどの技量をもっていたようで、喜寿庵の作庭にはうってつけの人材でした。白楊はこの岩山の凸凹を利用して2筋の水を流しました。岩盤に取り付くように生えていたマツなどもあえてそのままにして、山中の急峻な滝流れを表現することに成功します。
清浦奎吾は、独特の工夫を凝らしたこの庭に大変満足したようで、喜寿庵落成の折には、皇族を招待し盛大な開園祝いを行いました。
喜寿庵は、清浦奎吾の没後に都ホテルに寄贈され、この敷地には昭和34年(1959年)に宿泊施設の佳水園が新たに造られました。設計は、後に文化勲章を受章した建築家・村野藤吾です。庭園の平坦部は、岩盤の裾に流れを設け、白砂の平庭とする再整備を村野が指導しましたが、岩盤の流れ自体は白楊のものが残されました。
実は、昭和の葵殿の作庭に、白楊は関わっていません。白楊は喜寿庵の庭の完成後間もなく死去し、父の植治も葵殿の庭の完成直前に亡くなったため、葵殿の庭と佳水園の庭は、父子2人の遺作となりました。
見所・みどりの情報
葵殿庭園は、ホテル4階にある宴会場から眺めることができます。石組と大きくうねって池に注ぐ滝流れの下流部が険しい山のような景観をつくり、ガラス越しに迫ってきます。
佳水園の庭は、ホテル7階から歩いて訪れることができます。村野藤吾の設計の建物は、戦後を代表する数寄屋建築の名作として知られています。水辺にはツワブキ、オモトなどが、岩の上や周りは、木肌を出すため幹が磨かれたアカマツのほか、アセビ、モミジなどが、背景には華頂山の林があって独特の眺めをつくっています。
このほか、建物に囲まれた中庭には、彫刻家・井上武吉が造った「哲学の庭」があります。造形的な滝で、各階から眺めることができます。また、敷地内には「野鳥の森・探鳥路」の散策コースがあり、京都市街を見渡せる展望場所、「野鳥の水浴び場」、「あじさい園」などがあります。このように、同ホテルでは、造形的なものから自然まで様々な「緑」の姿に触れることができます。
手入れのポイント
これらの緑は、ホテルに所属する5人の職人さんにより毎日手入れされています。庭園の流れでは、ゼニゴケの繁茂を防ぐため、農薬を使わずに食酢で抑えたり、野鳥の森・探鳥路では、サクラ、モチツツジなど花木を植える一方、アオハダ、ウラジロ、クヌギなどの周囲の植生を守っています。「周りの環境に気を配りながら、お客様が楽しめるように工夫しています」と職人さんは話しています。
文化財の指定/関連の文化財
葵殿庭園と佳水園庭園(白楊氏作庭部分)は、植治・白楊父子が最晩年に技量を尽くして作った庭として、平成6年(1994年)、京都市の名勝に登録されました。
ご注意
庭園は、一般の人でも、ホテル利用者の迷惑にならない限りホテル保安課に申し出た上で見学できます(日没まで)。管理上、見学できない部分があります。
引用・参考文献・資料提供
【引用・参考文献】・京都日出新聞(1924年6月~1926年12月分)
・伯爵清浦奎吾伝、井上正明、1935、伯爵清浦奎吾伝刊行会
・都ホテル100年史、株式会社都ホテル、1989
・植治の庭、尼崎博正、1990、淡交社
・石と水の意匠-植治の造園技法、尼崎博正、1992、淡交社
・京都市の文化財(第12集)、京都市文化財保護課、1994
・都ホテル葵殿庭園及び佳水園庭園、尼崎博正、1994、株式会社都ホテル
【取材協力および資料提供】
ウェスティン都ホテル京都