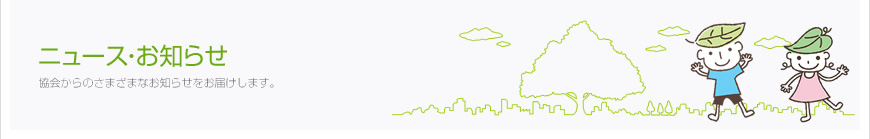【再掲】宝が池連続学習会 開催のお知らせ
2014年6月19日更新
妙法の送り火が行われ、人々の暮らしを支えてきた、宝が池の森。その豊かな自然は、京都に住む多くの人に親しまれてきました。しかし、現在、シカの 食害やナラ枯れによって、その自然環境は荒廃し、危機的な状況に陥っています。身近な森が発するSOSに対して、私たちには何ができるのでしょうか?
生物多様性豊かな森づくりにむけて、市民モニタリング調査の意味や手法など実践的な内容を学び、宝が池の森を次世代につなぐ行動へとつなげましょう。
昨年度は、5つのテーマ・5つの視点から 宝が池周辺の森の現状と問題点について学んだ「宝が池連続学習会」今年後は、さらに実質的な活動にむけて、まずは 現状把握+情報発信に力を入れた学習会「市民モニタリング」の視点を重視した講座を開催いたします。
全6回の連続講座となっていますが、1回のみの参加もOKです。
【講座概要】
■期間 : 2014年6月~2015年3月
■主な会場 : 宝が池公園周辺(フィールドワーク)および上高野防災会館(座学・子どもの楽園に隣接)
■参加費 : 1000円(一般) 500円(学生) ※6回分。必要に応じて 材料費等必要になる場合あり
■主 催 : (公財)京都市都市緑化協会/京都府立大学森林科学科
■申込み : お名前・年齢・(所属)・ご連絡先を明記の上、FAXもしくはE-mail、お電話で、下記宛て先までお申込みください。
■申込み先 : (公財)京都市都市緑化協会 宝が池子どもの楽園管理事務所
『宝が池連続学習会 係』
TEL 075-781-3010 / FAX 075-781-4422
kaerusenpai@kyoto-ga.jp
(チラシの記載内容が更新されました(6月20日))
【講座詳細】
●第1回●
日時 6月14日(土) 10:00~15:30
テーマ 「生きもの調査からはじめる 身近な森の生物多様性①」
~市民調査をはじめよう~市民調査の意義・調査結果を計画へつなげるための視点
多くの目で様々な情報を得ることができる市民調査。観察や調査の意義を知り、情報の読み取り方から活かし方まで一連の流れについて、他都市での事例等とともに学びます。午後からは、フィールドに出て、簡易調査の実践を行います。
・座学 : 徳島大学教授 鎌田磨人氏
・フィールドワーク : いきもの調査・シカ害調査の体験
*昆虫調査アドバイザー : 京都工芸繊維大学准教授 齊藤 準氏
*その他 アドバイザー予定
公開セミナー
※公開セミナーのみご参加の方は、参加費無料・お申込み不要です。直接会場までおこし下さい。公開セミナーの会場は、京都府立大学・第7会議室になります。
日時 7月13日(日) 14:00~16:30 (受付13:30~)
テーマ 「ナラ枯れ後の森林再生・シカと共生する森づくりを考える」
・講演 : 『事例から探る森づくり ~奈良・春日山の事例~』 大阪産業大学 教授 前迫ゆり氏
・意見交換会 : 宝が池の森づくりに関わる研究者や市民団体の方を交えて意見交換をおこないます。
●第2回●
日時 7月13日(日) 19:00~21:00 (公開セミナー後に開催します)
テーマ 「生きもの調査からはじめる 身近な森の生物多様性②~ナイトウォッチング~」
・講師 : 京都大学(農学研究科)講師 高柳 敦氏 (講師が決定いたしました。(6月20日))
ナイトウオッチングでは、ふだんは見れない生物の姿を見ることができます。夜の宝が池の森を歩きながら、新たな調査アイデアを考えるとともに、夜に人が入ることによるシカの行動への影響などについても考えてみます。
●第3回●
日時 9月13日(土) 10:00~15:30
テーマ 「MAPづくりをはじめよう!魅力ある森の利用・森育てを始めるために」
・座学① : 京都府立大学 教授 田中和博氏
・座学② : 京都学園大学 丹羽英之氏
生物多様性豊かな森づくりに向け、計画づくりの手順を知るとともに、調査などで得た情報を整理し、発信していくための「情報マップ」づくりのノウハウを学びます。
わかりやすく、利用しやすい記録からマップ作成までの過程を体験していきます。
●第4回●
日時 10月26日(日) 10:00~15:30 ※日程が変更となる場合があります。
テーマ 「宝が池界隈をめぐる、生物多様性ツアー」
・講師 : 京都府立大学(生命環境科学研究科)准教授 福井 亘氏
秋の宝が池の魅力を再発見する生物多様性ツアーを行い、子どもたちも含めた多くの人たちの目で、楽しみながら情報を収集します。いくつかのテーマから宝が池界隈をめぐり、多様性豊かな動植物とその環境を支えてきた人の営みについて考えてみます。
●第5回●
日時 12月21日(日) 10:00~15:30 (日程が変更になりました。(6月20日))
テーマ 「冬の森の利用と手入れ ~冬の森を楽しもう~」
・講師 : 京都大学(農学研究科)教授 柴田 昌三氏
京都府立大学(生命環境科学研究科)助教授 長島 啓子氏 (講師が決定いたしました(6月20日))
コバノミツバツツジが咲き誇り、どんぐりが豊かに実る森を引き継ぐために、ナラ枯れ後のシカによる被害が進む森の現状と、次世代の森育てにむけた試行の現場を学びます。フィールドでは、実生の育成作業や朽木の利用など森の循環を促す作業を行います。
●第6回●
日時 2015年3月14日(土) 10:00~15:30
テーマ 「宝が池界隈の歴史からみる森の利用とくらし」
・講師 : (公財)京都市埋蔵文化財研究所 吉崎 伸氏
宝が池の森には人と森とが共に暮らしてきた歴史があり、地域で引き継がれてきた知恵や技、ルールが生物多様性豊かな環境を支えてきました。自然と地域の暮らしの関係を見つめなおし、歴史的視座からその魅力を活かした地域づくりと発信の方法を考えます。
【お問合せ】
(公財)京都市都市緑化協会 宝が池子どもの楽園管理事務所
TEL 075-781-3010
e-mail:kaerusenpai@kyoto-ga.jp